今から150年前、日本に「郵便」が誕生しました―.
今や国民にとってなじみの深い「郵便」ですが、
その始まりの経緯については、意外に知られていません。
日本の「郵便」はどのような経緯で誕生し、
実態はどのようなものだったのでしょうか?
意外と知らない郵便の歴史を学べば、
いつもの日常も変わって見えてくるかもしれません。
ショッピングや観光と合わせて是非立ち寄ってみてください。
「心ヲツナグ 世界ヲツナグ」をコンセプトに、
日本最大約33万種の切手や郵政と通信の関係資料を展示。
スカイツリーを模したポストに手紙の投函もでき、
来館の思い出にもなります。
こじんまりとした家族で楽しめる博物館です。
下記クリックで好きな項目に移動します☆
郵政博物館とは?
2013年に閉館した逓信(ていしん)総合博物館の一部を
引き継いだ施設で、2014年3月1日にオープン。
墨田区押上にある博物館で、運営は公益財団法人 通信文化協会。
郵政博物館の主な収蔵品・展示品
世界各国の切手約33万種

ここには万国郵便連合(UPU)に
加盟する国々の2000年代初めまでの
切手33万種が展示してあります。
切手には各国の文化芸術、歴史が描かれています。
《世界最初の切手は、1840年使用開始5月6日》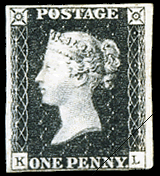
イギリスで発行された1ペニー(One Penny)と
2ペンス(Tow Pence)の2種類の切手です。
この切手は、色と料金から黒のインクを使った
 「ペニー・ブラック」と
「ペニー・ブラック」と
青色のインクを使った「ペンス・ブルー」。
と呼ばれました。
重要文化財エンボッシング・モールス電信機

嘉永七(1854)年、
日米和親条約締結のため2回目の来日時に
ペリー提督が、米国大統領から徳川幕府への献上品の一つとして
持参したものです。
中央のプレートには「For the Emperor of Japan」と彫刻があります。
エンボッシング・モールス電信機は、送信側でモールス符号を打つと、
受信側の電信機の紙テープにエンボス(凹凸の傷がつく)されて、
信号を送ることができます。
ペリーは、電線や電池など装置一式を持参し、
横浜の応接所から約900mの間に電線を架し、通信実験を行いました。
日本の電気通信の幕開けとして
平成9(1997)年に、国の重要文化財に指定されました。
ブレゲ指字電信機 日本で電報がスタートして150年!
《左:送信機,中央及び右端:受信機》
送信機の取っ手を回転させて刻印された文字を指示することで
電流が流れ、受信機の針も指定された文字の位置まで
回転するといった仕組みのものでした。
2002年に国の重要文化財に指定されています
平賀源内エレキテル

源内は長崎で学んでいた際、
オランダから輸入された
壊れたエレキテルを見つけます。
説明書も何も無いが、
源内はエレキテルを持ち帰り、
復元を試みます。
そして、約7年の歳月をかけ、当時の日本で入手可能な材料で
復元に成功しました。
日本初の鉄製赤色ポスト(俵谷式ポスト、中村式ポスト)の実物大復元模型

《俵谷》
明治の発明家俵谷高七氏が考案。
現在のポストの原形に近い特徴を備えています。
明治34年(1901)に試験的に設置されました。
《中村式》
中村幸治氏の考案によるもので、
明治34(1901)年に試験的に設置されました。
赤色鉄製の円筒形で、差入口に雨よけがついています。
ポストはなぜ赤い? ポストの歴史

ポストは時代とともに、少しづつ進化していきました。
手紙が日本で広まり、切手が始まった同じ年にポストは生まれました。
当初のポストは木でできた箱でした。
郵便の規模が拡大していくにつれ、
きちんとしたポストが必要になり始めたことで、
黒色のポストが日本に増えていったのです。
さらにそこから時が経ち、
1908年には正式に赤色の鉄製のポストが誕生し、
黒から赤色に変わった理由は、目立つ色にするためだと言われています。
また、通行人の迷惑にならないよう、形も丸くする工夫もされました。
木から鉄に変えることで、
火災からも守ることができるようになったのですね。
お年玉年賀はがきの発売はいつから?
1949年に初めて発売された、
お年玉くじ付きの年賀はがき。
右側が寄附金付きです。
考案したのは、
京都在住の民間人男性でした。
自作のはがき見本やポスター案を携え
郵政大臣に掛け合った
奮闘エピソードをご紹介します!
《考案者の林正治さんが作成した、お年玉付き年賀はがきの見本》
戦後の混乱で消息不明になった人の無事を確かめ、励まし合いたい!
”そこで、みんなが年賀状を出したくなるアイデアがないか?”
そこで、くじ付き年賀はがきを考案!
景品にはミシン、自転車、電化製品などはどうか?
昭和24年当時、一般人の月収は約8000円程度、
ミシンは20000円の時代でした。
自作のポスター持参で、
大阪郵政局にアタック!
昭和24年7月に東京郵政省にもアタック!
林正治さんのアピールポイント!!
郵便料金2円のうち、1円の寄付金を付けることで
生活困窮者に回すといったアイデア。
郵政事務次官 大野勝三氏に相談
戦後の赤字続きの郵政事業もあり賛同してくれ、
その後、とんとん拍子に話がすすむ。
自家製のくじ付きはがきを無料で配り、ボランティアで販促も行う。
こうして、12月1日にお年玉くじ付き年賀はがき発売!!
(寄付金付き 1億5000枚 寄付金なし3000枚)
郵政省の一大キャンペーン
 《第1回お年玉年賀はがきの賞品》
《第1回お年玉年賀はがきの賞品》
特等:ミシン
1等:純毛洋服地
2等:学童用グローブ
3等:学童用こうもり傘
12月下旬には完売!
翌年には4億枚発行
因みに、
《お年玉付き年賀はがき令和2年度賞品》
特賞 東京オリンピック観戦チケット
1等 現金30万円または電子マネー31万円
2等 ふるさと小包
3等 切手シート
《博物館詳細》
〈休館日〉月曜日(月曜日が祝日の場合は翌火曜日)
〈開館時間〉10:30~16:30分(入館は16:00まで)
〈観覧料〉大人300円/小・中・高校生150円
障がい者手帳をお持ちの方と介助の方は無料
お問い合わせ 03-6240-4311(郵政博物館)






